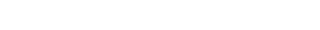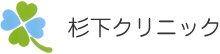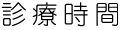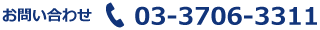内科
抗菌薬
抗菌薬とは細菌に対して増殖を抑えたり殺したりする薬剤の総称です。
以前は「抗生物質」とか「抗生剤」といういい方をしましたが、抗生物質とは微生物が作った病原体を殺す物質です。
(例えばアオカビから作られたペニシリンは最初の抗生物質です)
現在では化学的に合成された薬が主ですから、抗生物質を含めて「抗菌薬」といういい方が一般的です。
抗菌薬にはさまざまな種類がありますが、それぞれに効果的な細菌と効果が期待できない細菌があります。
厳密には細菌培養検査と薬剤感受性検査を行わないと、効果があるか否かはわかりません。
が、その検査には日数がかかるので、実際の臨床の場ではしばしば「効果がありそうな抗菌薬」を投与します。
もともと効果があった抗菌薬に対して、細菌はしばしば変異して「耐性菌」となります。
その一方、新たな抗菌薬が開発されますので、細菌と抗菌薬の関係は「いたちごっこ」のようなものです。
抗菌薬を頻繁に使用すると、抗菌薬の効きにくい多剤耐性菌が生れます。MRSA(メキシリン耐性ブドウ球菌)が代表的なものですが、近年多剤耐性菌の種類は増加しており医療の現場では大問題となっています。
また、抗菌薬を長期に続けることにより腸内の細菌のバランスがくずれて、ある種の腸炎を起こすことがあります。
ウィルス感染には抗菌薬は効果がないので、いわゆる風邪などに対して抗菌薬は通常投与しません。