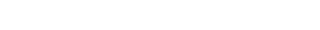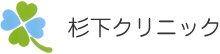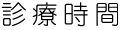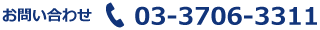内科
誤嚥性肺炎
口の中の食物や唾液が本来の通り道の食道ではなく、気管や気管支に流れ込むことを誤嚥といいます。
誤嚥により起こる肺炎が誤嚥性肺炎です。
高齢者に多く発症し、脳血管障害、神経筋疾患、認知症、胃食道逆流症、のどの動きに関わる神経の麻痺、鎮静薬の投与などで起こりやすくなります。
明らかにむせた後に起こるだけではなく、呑み込みやせき込みの機能が低下すると自分では気づかない間に発症することもあります。
典型的な症状は発熱、喀痰、呼吸困難などです。
ただし高齢者の場合はこれらの症状がみられないことも多く、レントゲン等でも軽微な変化しか認められないこともあります。
その場合は急速に悪化することもありますので注意を要します。
口の中などの細菌感染が原因となりますので、治療にはそれに適した抗菌薬を用います。
高齢者の誤嚥肺炎では全身状態の良くないケースもありますので、その場合は病院に依頼して入院治療をする必要があります。
誤嚥性肺炎は反復することが多いので予防が重要です。
口の中を清潔にする、呑みこみの訓練、食事の工夫(とろみをつけるなど)、食後すぐに横にならないよう注意する、などがあげられます。
また、肺炎球菌ワクチンを接種して肺炎を予防するのも勧められます。